![]()
![]() 緑ヶ丘区 弁護士 衛藤二男 ②
緑ヶ丘区 弁護士 衛藤二男 ②
827号 2016年10月23日
(31)自然災害による被災者の
債務整理に関するガイドライン②
「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」(以下、本ガイドライン)に基づいて債務整理を申し出ることができる債務者の要件については、前回に簡単に説明しましたので、今回は少し詳細に説明しましょう。
① まず、要件の1つである「住居や勤務先等の生活基盤や事業所、事業設備、取引先等が熊本地震の被害を受けたことにより、現在負担している住宅ローンや住宅リフォームローン、事業性ローンその他の債務を弁済できなくなっていること、又は近い将来その債務の弁済をできなくなることが確実に見込まれる」ということです。
これは、熊本地震で被害を受けた結果、債務の返済ができなくなった又は近い将来困難になることが確実であるという、因果関係が必要であるということです。したがって、熊本地震よりも前から既に債務の返済が困難になっていた等の事情がある場合は、本ガイドラインは使えません。
債務の返済ができない又は近い将来その返済が困難になることが確実かどうかは、債務者の財産や収入、信用等の資産、債務総額、返済期間や利率等の返済条件、家計の状況等を総合的に判断して決められます。債務者の資産には、地震による被災者へ給付される被災者生活再建支援金、災害弔慰金や災害見舞金、義援金等も含まれますが、熊本地震の場合は、これらの支援金や義援金は、債務の返済に充てられるものではないとして、債務者の返済能力を判断する際の資産としては考慮しなくてもよいことになっています。
② 次の要件は「弁済について誠実であり、負債を含む財産の状況を債権者へ適正に開示している」ということです。これは、債務整理の申し出をして、本ガイドラインに適合する債務整理案(調停条項案)を作成するについて、債権者へ提出する債務整理申出書や財産目録・債権者一覧表の記載に虚偽の記載がされておらず、提出可能な添付資料も誠実に提出されていることを意味します。
③ 次に「熊本地震が発生する前に、現在負担している債務について、期限の利益を喪失させる事由がなかった」という要件です。「期限の利益」というのは、債務の返済条件として、債務の総額を一括返済するのではなく、毎月一定の期日までに多数回に分割して返済することによる債務者の受ける利益のことです。通常は2〜3回、毎月の期限までの返済を怠ると当然に分割返済ができなくなり、残債務の一括返済と遅延損害金の支払いをしなければならなくなります。このことを「期限の利益を喪失する」といいます。
その他に4つほどの要件がありますが、これらは債務者を無償で支援してくれる登録支援専門家(弁護士)が専門的な観点から判断しますので、省略します。
次回は、本ガイドラインに基づく債務整理の申し出手続きのお話です。
832号 2016年11月27日
(32)自然災害による被災者の
債務整理に関するガイドライン③
最終回は、まとめとして、この債務整理の申し出から終了までの手続きの概要をお話します。
◆1 債権者への手続き着手の申し込みと同意
①まず、熊本地震による被災者(債務者)は、住宅ローンを組んだ金融機関(債務の元本総額が最大の債権者で、主たる債権者といいます)に対して、本ガイドラインに基づく債務整理手続きに着手する旨を書面で申し出ます。
②この債務者からの申し出に対し、主たる金融機関は申し出を受けてから10営業日以内に、その申し出に同意するかどうかを書面で回答します。
◆2 登録支援専門家の選任依頼とその委嘱
①次に、メインの金融機関から債務整理の申し出について同意を得た債務者は、関係機関(弁護士会、公認会計士会、税理士会、不動産鑑定士協会等)を通じて、全国銀行協会(全銀協)に対し、関係機関に登録された登録支援専門家を委嘱することを依頼します。
②全銀協から推薦依頼を受けた関係機関は、登録支援専門家を全銀協へ推薦し、その推薦に基づいて全銀協は登録支援専門家の委嘱をします。ほとんどの場合、初めに弁護士が登録支援専門家として委嘱され、必要に応じて不動産鑑定士等が委嘱されているようです。
◆3 債権者への債務整理の申し出
①登録支援専門家が決まると、債務者は登録支援専門家の援助を受けながら、メインの債権者(金融機関)のみならず、原則として全ての債権者に対して、書面により債務整理の申し出をします。
②その申し出の際には、財産目録、債権者一覧表、陳述書(事情説明書)その他必要書類を揃えて、これを債権者へ提出します。
③注意しなければならないのは、この債務整理の申し出があった時点から債務整理の終了するまでの期間(これを一時停止期間といいます)は、債務者は一定の場合を除いて資産の処分等や新たな借入ができなくなるし、債権者も弁済を受けたりすることができなくなります。これに違反すると、本ガイドラインに基づく債務整理手続きの利用を拒否されます。
◆4 調停条項案の作成・提出と債権者の同意
①債務整理の申し出の後、一定期間内に、債権者に対して、債務の弁済に関する調停条項案を作成して提出しなければなりません。
②この調停条項案には、いくつかの要件がありますので、登録支援専門家の助言等を受けながら作成します。
③調停条項案の作成に際して、債権者との事前の協議をすることもあります。
④調停条項案について、全ての債権者の同意が得られたら次の段階へと進みますが、その同意が得られないかまたは得られる見込みがないときは、債務整理手続きは不成立となって終了します。
◆5 特定調停の申し立てへ
①調停条項案について債権者の同意を得た場合(同意の見込みを得た場合も含む)、債務者は、簡易裁判所へ特定調停の申し立てをします。
②特定調停手続きにおいて調停条項案が調停調書へ記載されて同手続きは終了し、これと同時に、本ガイドラインに基づく債務整理手続も終了します。
③その後は、債務者は、調停条項に従って返済していくことになります。
衛藤二男法律事務所
TEL 282−8251 FAX 282−8261
受付時間 午前9時半〜午後5時半(月〜金)
836号 2016年12月25日
(33)震災ADR
今年の最後の「知って得する法律相談」は、熊本県弁護士会が実施している「震災ADR」という紛争解決方法を紹介します。
ADRというのは、裁判所の訴訟手続等によらない紛争の解決手続きで、熊本県弁護士会が実施している「震災ADR」は、熊本地震の震災に関連する紛争について、熊本県弁護士会所属の弁護士が、中立的立場で「和解のあっせん人」となって紛争当事者の言い分を聴取し、解決のための「あっせん案」を提示して紛争を解決する手続きです。
熊本地震の発生後は、建物損壊に伴う賃貸借関係のトラブル、被災したマンション等の修繕、解体等を巡るトラブル、ブロック塀の倒壊や屋根瓦の落下等に関連するトラブル等、いわゆる相隣関係(お隣同士)の紛争が非常に多く発生しました。そこで、熊本県弁護士会では、安い費用で早期の紛争解決を図る方法として「震災ADR」を実施することにしました。
1.「震災ADR」申し立て前の準備
①申し立てを希望する人は、熊本県弁護士会所属の弁護士の法律相談を受け、その相談担当弁護士から「震災ADR」申し立ての紹介を受けることが必要です。
法律相談センター ℡ 096−325−0009相談料は無料です。
②ただし「震災ADR」案内のチラシの裏面の申込用紙に必要事項を記入し、熊本県弁護士会紛争解決センター(以下、紛争解決センターといいます)宛てに郵送又は FAX 096−325−0914で申し込むこともできます。この場合は、申立サポート弁護士から内容確認の電話等をさせていただきます。
2.申し立て手続き
①上記1−①の場合は、弁護士による法律相談を受けられた人は、紛争解決センター宛てに、相談担当弁護士の「紹介状」を添付した「和解のあっせん申立書」を提出して申し立てをします。
②上記1−②の場合は、「震災ADR」案内チラシ裏面の申込用紙に必要事項を記入後、紛争解決センターへ郵送又はFAXで送付し、申立サポート弁護士の電話等による内容確認を経て申し立てをします。
3.申し立ての受け付け
①あっせん期日の指定 申し立て手続きの後、あっせん人(弁護士)、申立人及び相手方の日程を調整して、第1回のあっせん期日が指定されます。
②この期日の指定の際に、相手方には話し合いに応じるように要請します。もし、相手方が話し合いによる解決に応じる見込みがないときは、手続きを進めることができませんので手続きは終了します。
4.あっせん期日
①あっせん人は、あっせん期日において当事者双方から、原則として別々に言い分を聴取し、合意ができるようにあっせんを行います。あっせん期日の回数は原則3回以内です。
②相手方が期日に出席して話し合いを重ねたが合意することができなかった場合は、あっせんは不成立となります。
5.和解の成立
①合意が成立したときは、あっせん人が「和解契約書」を作成し、当事者双方がその内容を確認して手続きが終了します。
②その後、和解成立手数料として一定額を申立人と相手方が費用を折半して負担していただきます。
6.費用等の詳しいお問い合わせ
紛争解決センター ℡096−325−0913
840号 2017年1月29日
(34)家族信託①
今年の第1回目は「家族信託」という制度についてです。相続や遺言ということについては多くの方がご存知だと思いますが、「信託」「家族信託」という制度は、最近取り上げられて関心が持たれるようになりました。今回からできるだけ分かりやすくお話したいと思います。
◆そもそも「信託」とは何ぞや?
「信託」とは、ある人(委託者)が、契約や遺言により、自分の有する土地や金銭等の財産(信託財産)を自分の信頼できる人(受託者)に移転し、委託者の定めた信託の目的に従って信託の利益を受ける人(受益者)のために、受託者が信託財産を管理・処分等をするという制度です。
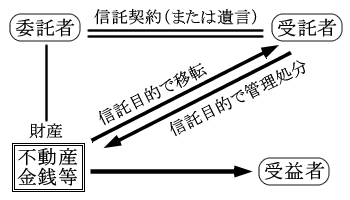
◆分かりやすい事例
Aさんは現在75歳。72歳の認知症の妻Bとの間には長女C(45歳)と長男D(42歳)がいる。Aさんには、収益不動産(賃貸マンション、年間賃料収入約500万円)がある。しかし、長男Dは無職・無収入で浪費癖があり、両親や姉に金の無心をすることがしばしばある。
Aさんは、認知症の妻Bの生活や、DがAさんの財産を相続してもすぐに浪費してしまうのではないか、また、自分の死後の相続でもトラブルを起こすのではないかと心配している。
Aさんの不安を解消する方法には何があるか。この事例を前提として、Aさんの取りうる方法について、遺言をした場合と信託を利用した場合で考えてみましょう。
●Aさんが遺言をする場合
Aさんは現在、認知症にもなっておらず、財産関係についても判断能力が十分あるので、自分の財産のことを慮(おもんぱか)って遺言することが考えられます。
遺言の方法にはいくつかありますが、最も確実な方法は公正証書による遺言をすることでです。公正証書遺言のやり方については別の機会に説明しますが、事例との関係でどのような内容の遺言にするかを次回から考えてみましょう。
衛藤二男法律事務所
TEL 282−8251 FAX 282−8261
受付時間 午前9時半〜午後5時半(月〜金)
844号 2017年2月26日
(35)家族信託②
今回は、前回の事例を図示しましたので、それを参考に説明します。まず、事例において考えられるAさんの遺言について考えてみましょう。
遺言する場合に重要で大きなポイントは2つです。まず、遺言者がご自身の財産(将来の遺産で、遺言の対象となる財産)を正確に把握しておくことです。次にその財産をどの相続人に、どのように相続させるかということ、すなわち、遺産の分け方の問題です。なお、遺言をしていなければ、民法が定める法定相続分に従うことになります。
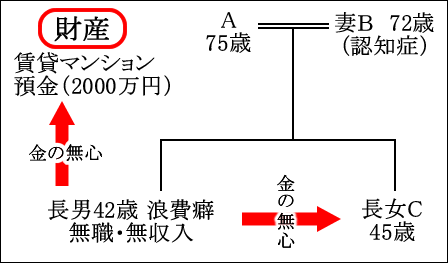
まず、Aさんの妻が認知症ということですから、自分の亡きあとの妻Bさんの生活のことが一番の心配事ではないでしょうか。そこで、自己の財産のうち、妻Bさんの生活費や施設費(将来、施設に入所することが予想される)のために、定期的な収入である賃貸マンションの賃料収入をBさんに相続させることが考えられます。なお、Bさんは認知症で自己の財産管理能力に問題がありますので、別途、成年後見制度の活用を考慮する必要があるでしょう。特に長男Dさんからの金の無心のおそれがありますので、そのことからもBさんには成年後見人が必要と思われます。ただ、遺言により成年後見開始の申し立てはできませんので、これをAさんがするとすれば、Aさんの生前にすることになるでしょう。
次に無職・無収入で浪費家の長男Dさんについてですが、遺留分がありますから、相続開始後において、遺留分による紛争が起こらないようにしたいものです。そこで、遺言でDさんの遺留分を考慮し、その分をDさんへの相続分として遺言しておくと良いでしょう。なお、Dさんが被相続人に対して生前に暴力をしていた等の事情がある場合など、一定の場合には家庭裁判所へ相続人廃除の申し立ても考えられますが、これは容易に家庭裁判所で認められません。またDさんの浪費癖からすると、相続で取得した遺産は浪費によってすぐになくなってしまうことが予想されますが、Dさんの財産管理能力に問題がない以上、浪費による財産の散逸は防止できません。
以上に加えて、遺言はあくまでも相続開始後に効力が発生するものですから、相続開始前のAさんの心配事の解決には役立ちません。
では家族信託という制度を使うとどうなるでしょう。次回に続きます。
852号 2017年4月23日
(36)家族信託③
前回に引き続いて家族信託のお話です。まず、前回の事例を家族信託の図で示すと下記のとおりです。
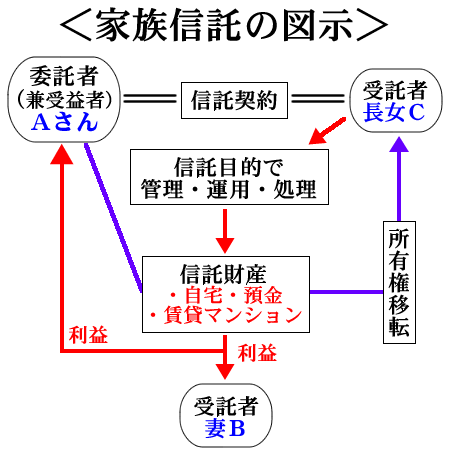
Aさんの心配事の第一は、認知症の妻Bさんの生活の安定です。Bさんが施設に入所した場合の安定的な費用の工面をAさんの生存中のみならず、Aさんが死亡した後でも保証してあげることです。心配事の第二は、長男Dさんの浪費癖(これは容易には治らないでしょう)から、Aさんの財産をいかにして守るか、ということです。
Aさんのこのような心配事を解決するために、利用することが考えられる方法が家族信託という制度です。
まず、Aさん(委託者)は、受託者である長女Cさんと信託契約を結び、自己の財産(自宅・賃貸マンション・預金)を受託者である長女Cさんへ「信託の目的」で所有権を移転します。このように信託の目的で受託者へ移転された財産を「信託財産」といいます。家族信託での「信託の目的」とは、受託者が信託契約でなすべき目的のことであり、具体的には「信託財産を管理または運用し、もしくは処分して、その利益を受益者に定期的に給付し、受益者の安定した生活および福祉を確保すること」ということになります。
受託者となった長女Cさんは、自分の所有している固有の財産とは区別して、「信託の目的」に従って、信託財産を管理・運用または処分し、そこから生まれてくる利益を受益者へ給付しなければなりません。
受益者とは、信託契約によって信託の利益を受けるものとして指定されたものです。委託者自身も受益者になることができます(これを自益信託といいます)ので、事例の場合は、Aさん本人も受益者を兼ねることができます。
事例では、Aさんの心配事の第一は妻のBさんの生活の安定ですからBさんを受益者とすることがまず考えられます。ただ、Aさんが生存中は、Aさんの生活の安定もありますので、信託財産からの利益をAさんも受け取れるように受益者とすることになります。
受託者(事例では長女のCさん)も受益者になることができますし、長男Dさんも受益者に加えることもできますが、Aさんの生存中は、自分と妻の生活のことを第一に考えて、当初の受益者とし、万一Aさんが死亡した時は、さらに二次的に受益者としてBさんや2人の子(Cさん、Dさん)を指定すればいいでしょう。
次回も家族信託という制度のお話を続けてお話します。
衛藤二男法律事務所
TEL 096-282-8251 FAX 096-282-8261
受付時間 午前9時半〜午後5時半(月〜金)
860号 2017年6月25日
(37)家族信託④
これまでの事例のお話では、Aさんの心配事は、長男のDさん(42歳)が無職・無収入で浪費癖があり、両親や姉のCさんに金銭の無心をすることがしばしばある。そのため、父Aさんを長男Dさんが相続すると、その相続財産をすぐに浪費してしまうのではないか、ということでした。(下図参照)
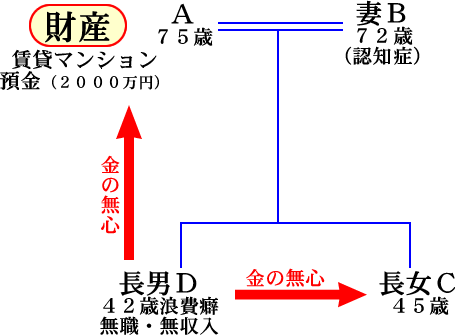
そこで、Aさんは、Dさんには相続させないような遺言をすることも考えられますがDさんには遺留分があります。また、かつては「準禁治産宣告」の原因とされていた「浪費」は、成年後見制度である補助、保佐、成年後見の開始原因でもありませんので、これらの利用もできません。
●家族信託を利用すると
委託者兼当初受益者としてAさん、受託者に長女のCさん、当初受益者のAさんの死後は、二次受益者として妻のBさん、三次受益者としてCさんとDさんを指定します。この場合、CさんとDさんは均等の割合で受益権を取得するとしておきます。そして、Dさんには毎月の生活に必要な一定の金額のみを受託者Cさんから給付する、という規定を定めておくと良いでしょう。
こうすることにより、Dさんは遺産を取得する権利は得られますが、相続と違って、毎月一定額の金銭を受け取ることができるに過ぎないので、少なくとも、Dさんの浪費にはブレーキがかかります。相続の場合は、遺産分割協議等によってDさんが相続する遺産が決まるとその相続分に相当する遺産は、そのままDさんが取得しますので、すべてがDさんの浪費の対象になってしまいます。
また、遺産から一定の金銭を受領できるのは、相続ではなく、信託契約に基づくものですから、受託者が信託契約に基づいて給付をすること自体も法的な根拠があることになります。
このように、信託という制度は、生前の契約により、遺言や遺産分割協議、法定相続等の相続制度とは異なる財産の管理・処分ができる制度といっても過言ではありません。
次回は、「遺言代用信託」と「受益者連続型信託」という2つの信託制度について説明しましょう。
868号 2017年8月27日
(38)負担付遺贈①
今回は、まず、以下の様な事例を設定してみます。この事例を前提として、現在の民法上の制度である「負担付遺贈」(民法1002条1項)の問題点を考え、その解決策を信託制度で見てみましょう。
◆事例
「Aさん(75歳)には認知症の妻のBさん(74歳)と長男C(45歳)、長女D(43歳)、次女E(40歳)の3人の子がいる。Aさんには、不動産(自宅の敷地・建物)と金融資産1000万円がある。
Aさんは、自分の死後の妻Bさんの老後の生活が心配になり、遺言により、長男Cには、遺産となる財産の中から他の2人よりも多額の財産を相続させる代わりに、妻BさんをAさんの自宅に引き続き住まわせ、生涯Bさんの生活支援を行うことを義務づけて遺言をしていた(負担付遺贈)。
ところが、長男Cは、Aさんの死後、初めの頃は母Bさんの面倒は見ていたが、そのうち生活の支援を停止し、更には、長女DにBさんを引き取らせてしまい、Aさんがした負担付遺贈で定めていたBさんの生活支援等をしなくなった」
このように、負担付遺贈の受遺者(遺贈を受ける人)がその負担の義務を履行しなくなった場合、他の相続人はどのような手段をとることができるでしょうか。
◆回答
負担付遺贈の受遺者がその義務の履行を怠った場合、まず、他の相続人は、当該受遺者に対して相当の期間を定めて義務を履行するように催告をし、それでも義務を履行しない場合は、その負担付遺贈をした遺言の取消しを家庭裁判所へ請求することができます(民法1027条)。
・負担付遺贈の取消請求の問題点
まず第一に、民法1027条の規定に従うこと自体、時間がかかります。そのことを一応置くとしても、遺言の取り消し請求を受理した家庭裁判所は受遺者から事情を聞きます。その際、受遺者は、「遺言で定められた義務をそれなりに果たした」とか、「母のBが妹(長女)Dのところへ行ったのはBが自分との同居を拒否し、自らの意思で出て行ったからであり、義務違反はしていない」ということを主張することは目に見えています。そのため、受遺者が義務を履行していないことを家庭裁判所に認めてもらうことに困難を伴います。
もちろん負担付遺贈の遺言は遺言者であるAさんが死亡しているので、遺言者Aさんがこれを取り消すことはできません。このように、負担付遺贈は、負担の義務を負っている受遺者がその義務を履行しなかった場合の手当てが十分ではないことが一つの問題点とされています。
◆その問題点を解消する方法
前記の負担付遺贈の問題点を解消する方法が、信託制度です。すなわち、信託制度は、受遺者の恣意的な主張や自分勝手な行動を規制し、遺言の目的の達成まで受託者(負担付遺贈の受遺者の立場に立つ人)を信託という制度で拘束し、受益者(事例での妻Bさん)の利益を保護するという制度です。
876号 2017年10月22日
(39)負担付遺贈②
前回は、Aさんが遺言により、認知症の妻Bさんの老後の生活を心配して、長男Cへ一定の財産を相続させる代わりに、Aさん亡き後の妻Bさんの生活支援を行うことを義務づける遺言(負担付遺贈)をした場合の問題点、すなわち、負担義務を負っている相続人(長男C)がその義務を履行しなかった場合の手当が不十分であるというお話しをしました。では、信託制度(信託契約)を利用した場合はどうでしょうか。
信託契約とは、前回の事例でいうと、委託者(Aさん)が、Aさん自身や妻Bさんの老後の生活が安心してできるようにするために(信託の目的)、委託者の財産を受託者(長男C)へ移転し、受託者は信託の目的に従ってその財産を管理・処分するということを合意する契約です。事例では、Aさんの亡き後の妻Bさんの老後の生活の安定を目的としていましたが、Aさんが自分の財産管理や生活の安定にも不安を覚えている場合は、それも信託の目的にすることができます。
委託者Aさんと長男である受託者Cとの間でこのような信託契約が締結されると、信託法により、受託者である長男Cにはさまざまな義務や責任が生じます。すなわち、受託者Cは、信託の目的に従って財産を管理・処分する責任を負っており、信託事務を遂行する上で様々な義務(例えば、受益者のために忠実に信託事務を処理しなければならない;信託法30条)が課されています。もし、これらの義務に反して信託財産に損害が生じたり受託者が不正行為をした場合、信託法は例えば、受託者の任務違背行為については受益者に差し止め請求権(信託法44条)や受託者を解任することも規定しています(信託法58条)。また、受託者が忠実義務に反する行為をして信託財産に損失を生じさせた場合は、受託者にはその損失を補填する責任も生じます(信託法40条3項・4項)。
さらに、受益者(本件では認知症のBさん、場合によってはAさんも)を保護するものとして、信託監督人や受益者代理人という制度もあります。
信託監督人は受益者(AさんもしくはBさん)が、受託者である長男Cを自ら十分に監督できないような事情がある場合に、受託者Cを監視・監督する第三者を信託監督人として自ら選任し、または家庭裁判所に選任の申し立てをする方法により選任します。受益者代理人は、受益者が適切に意思表示ができない場合や受益者が自ら権利行使することが困難な特別の事情がある場合に、受益者の保護と共に信託事務の円滑な処理を図るという観点から、受益者本人の代理人となって、信託に関する受益者の権利を行使する者です。
このように信託法は、受益者の利益を保護するために多くの規定を設けており、本件のような家族信託において、今後は信託制度の利用が期待されているところです。
893号 2018年2月25日
(40)賃貸借契約①
このたび、民法が大幅に改正され、改正民法が平成29年6月2日に交付されました。この改正民法は、一部を除いて、公布の日から起算して3年を超えない範囲内で政令で定められる日から施行されます。今回の知って得する法律相談は、この改正された民法の中から賃貸借契約に関して、取り上げてみたいと思います。
●簡単な事例
Aさんは、Bさんから建物を賃借して家族らと居住していますが、仕事の関係で別のところへ引っ越すことになり、建物を明け渡すことになりました。ところが、家主のBさんから、建物の居間のフローリングの床や壁紙の張替えが必要になったのでその工事代金を請求します、と言われています。Aさんは、Bさんの請求に応じなければなりませんか?
●解説
賃貸借契約において、契約が終了すれば借主は賃借物を賃貸人へ返還しなければなりません(民法601条)が、どのような状態で返せば良いのでしょうか。
まず、原則です。改正民法621条は、賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合は、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に回復する義務を負うと定めています。
次に例外その1です。同条は、その損傷が通常の使用及び収益によって生じた損耗や賃借物の経年変化による場合は除くとしていますので、その原状回復義務を負わなくても良いことになります。例外その2です。同条但書は、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由による場合はこの限りではないと規定していますので、この場合も原状回復義務を負わないことになります。
以上の民法の規定に対して、たとえば、賃貸人と賃借人との間の賃貸借契約で、フローリングの床や壁紙の通常の損耗や経年劣化についても借主がその損傷について原状回復義務を負うとか、その費用を負担する旨を合意していた場合は、どうなるでしょうか。このような場合は、借主がその合意に基づいて原状回復義務を負うことになります。
しかし、問題は、このような合意をしておけば、すべて、借主に原状回復義務を負わせて良いかということです。この点について、最高裁判所は、賃借人に予期しない特別の負担をさせないように、「少なくとも、賃借人が補修費用を負担することになる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項自体に明記されているか、仮に賃貸借契約書で明らかでない場合には、賃貸人が口頭により説明し、賃借人がその旨を明確に認識し、それを合意の内容としたものと認められるなど、その特約が明確に合意されていることが必要である」と判示しています。
賃貸借契約の終了に伴う原状回復義務を巡るトラブルは多発していますが、国土交通省もガイドラインを作成していますので、それも参考になります。
902号 2018年4月29日
(41)賃貸借契約②
◆相談内容
私はAさんに対し、「使用目的を店舗(弁当屋)、賃料を月額20万円、契約期間を5年間、店舗改装費用はAさんの負担、契約終了時は原状回復すること」を条件として、建物を賃貸し、その際、保証金として250万円を預かりました。
その後1年くらいすると、Aさんからの賃料支払いが度々滞るようになり、その額が5カ月分滞ってしまい、Aさんとの連絡も取れなくなりました。建物内にはAさんが造作した設備や什器備品がそのままで放置されたままです。
このような場合、私はどのように対応したら良いのでしょうか。
◆回答
まず、結論から述べると、あなたは、本件建物の賃貸借契約を賃料不払いという債務不履行を理由として契約解除し、建物の明渡請求と未払賃料の支払いを求める訴訟を起こし、その勝訴判決に基づいて建物明渡と未払賃料支払いの強制執行をすることになります。注意しなければならないのは、このような法的手続きを取らないで、貸主側が無断で建物内に入って借主の造作や什器備品を持ち出したり壊したりしてはいけない、ということです。たとえ建物を所有しているからと言って、第三者へ適法に賃貸している以上、当該建物の中に無断で入ったり賃借人の所有物を持ち出すのは、犯罪行為になる恐れがあります。自力救済は原則として禁止されていますので、十分注意が必要です。
ご相談では、借主のAさんと連絡が取れないので、契約解除の通知文書の宛先や訴状の送達先をどうするかということ問題となりますが、公示送達という方法もありますので、その点は大丈夫でしょう。
次に、保証金250万円を預かっていますので、これから回収することもできます。この度改正された民法第622条の2第1項では、名目のいかんを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務、要するに賃借人の賃貸借契約上の一切の債務を担保するために、賃借人が賃貸人へ交付する金銭を敷金と定義しています。本件でも「保証金」という名目で250万円をAさんから預かっていますが、これはまさに民法が定義する敷金に該当します。
敷金で担保される賃借人の賃貸借契約上の一切の債務ですから、未払賃料債務はもちろんのこと、賃借人の原状回復義務から生ずる金銭支払債務が担保されることになります。
民法第622条の2第2項では、賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の返済に充当することができるとしていますので、賃貸人において、預かっている保証金を未払賃料や原状回復費用に充当することができます。他方、賃借人の方から賃貸人に対して、敷金を未払賃料等の債務へ充当してくれと要求することはできません。
また、賃借人が賃貸人に敷金の返還を請求できるのは、原則として、賃貸借契約が終了して建物の明け渡しをした後、賃借人の債務の清算が終了してからになります。
909号 2018年6月24日
(42)離婚に関する慰謝料請求
今回は、離婚に関する慰謝料請求を取り上げてみます。
●相談内容
夫が勤務先の会社の女性と2年くらい前から浮気をしていることが分かりました。この女性は私の友人でもあり、私たちが夫婦であることは知っています。私たち夫婦には7歳と10歳の二人の子がいますが、最近は夫が家を空けることが多く、子どもたちとも触れ合うことがほとんどなく、なんとなく夫の行動に不信感を持っているようです。
そこで、夫との離婚を考えていますが、夫の浮気相手の女性に対して、私や子どもが慰謝料を請求することはできるでしょうか。
●回答
まず、民法752条は、夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならないと規定し、いわゆる夫婦の扶助協力義務を定めています。この扶助協力義務には、相互の貞操義務も含まれていますので、貞操義務に反する行為は「不貞行為」となり、これに加担した者は不法行為責任(民法709条)として損害賠償責任、すなわち慰謝料支払義務を負うことになります。
本件の不貞行為の相手方である女性は、故意、すなわちご主人が婚姻関係にあることを知って不貞行為に及んでいますので、妻であるあなたに対して損害賠償責任を負うことになります。この損害賠償責任は後に離婚するかどうかとは関係なく生じるものです。
他方、仮にご主人の不貞行為を原因として離婚せざるを得なくなった場合は、離婚原因を作り出したご主人はもちろんのこと、不貞行為の相手方女性に対しても、共同不法行為責任を追及することができますので、不貞行為を原因として離婚することになった精神的苦痛に対する損害賠償として、一定額の慰謝料を請求することができます。
慰謝料の額は、夫婦の婚姻関係の継続期間、不貞行為の程度・頻度、態様、不貞行為の相手方の態度等に基づいて総合的に判断され、決まった計算方式はありませんが、大体100万円から300万円位が多いようです。
ところで、離婚した場合に、お二人のお子さんが父親を奪った不貞行為の相手方に対して、慰謝料の請求ができるでしょうか。
この点について、最高裁判所は、「未成年者の子が日常生活において親から愛情を注がれ、その監護、教育を受けることができなくなったとしても、害意をもって積極的に阻止するなど特段の事情のない限り、その子に対する不法行為とはならない」としています(最高裁判決・昭和54年3月30日)。「害意をもって積極的に阻止するなどの特段の事情」とは、たとえば、離婚した父親が子に対して経済的な援助をしようとする際に、今の家族を大事にしてほしいなどと言って積極的に援助を阻止したような場合がこれに当たるでしょう。したがって、このような事情がないときは、お子さんからの不貞行為の相手方女性に対する慰謝料請求は、原則として難しいと思われます。
917号 2018年8月26日
(43)葬儀費用について
≪相談の内容≫
葬儀費用は、相続財産の中から支払っても良いのでしょうか。また、葬儀費用は、本来は誰が負担するべきでしょうか。私は、父の死亡が突然であったために、やむを得ず自分の定期預金を解約して父の葬儀費用として200万円ほどを立て替えて支払っています。相続人である兄弟姉妹にも負担してもらいたくて相談しましたが、支払ってくれません。お香典も皆で分配するべきだともいわれています。
葬儀費用は、私が一人で負担しなければならないのでしょうか。お香典は、相続財産として分配するべきでしょうか。
≪回 答≫
 まず、葬儀費用は、被相続人の死亡後に発生した費用であり、その費用がたとえ被相続人のために使用されたとしても、被相続人が負担するべきものではありません。したがって、被相続人の相続財産(葬儀費用相当額の支払債務)ではなく、相続財産対象ではありませんから、遺産分割調停や遺産分割審判では解決できません。もちろん、相続人間で協議して誰がどのように負担するかが決まれば、その合意は有効ですから、その合意に従えばよろしいでしょう。問題は、相続人間で協議が整わない場合です。葬儀費用は、最終的に誰が負担するべきかということについてはいろいろな考え方があり、どれが正しいとも言えないのが現状です。
まず、葬儀費用は、被相続人の死亡後に発生した費用であり、その費用がたとえ被相続人のために使用されたとしても、被相続人が負担するべきものではありません。したがって、被相続人の相続財産(葬儀費用相当額の支払債務)ではなく、相続財産対象ではありませんから、遺産分割調停や遺産分割審判では解決できません。もちろん、相続人間で協議して誰がどのように負担するかが決まれば、その合意は有効ですから、その合意に従えばよろしいでしょう。問題は、相続人間で協議が整わない場合です。葬儀費用は、最終的に誰が負担するべきかということについてはいろいろな考え方があり、どれが正しいとも言えないのが現状です。
葬儀費用は、本来は喪主や相続人のために執り行う儀式ではなく、被相続人のために執り行うものですから、被相続人の社会的地位や資産の状況、交友関係などさまざまな要素があるために、その金額も千差万別です。また、地域によってもいろいろな決まりや慣習もあるためにそれも考慮することが必要です。
また、香典も被相続人の死亡後に喪主となる人が受け取るものですから、相続財産ではありません。被相続人の葬儀費用の一部に充てることを目的としているとも考えれていますので、通常は喪主が負担する葬儀費用の一部に充当することが許されると考えられます。葬儀費用の負担を全くしなかった相続人が、香典も相続財産と同じように相続人間で平等に分配するするべきだと主張することもよく聞くことですが、香典の趣旨からすると少し筋が違うとも言えます。
いずれにせよ、このように葬儀費用の負担や香典の分配の可否については、法律上の基準はありませんので、まずは当事者間で十分に話し合いをして解決するのが望ましいでしょう。
926号 2018年10月28日
(44)離婚裁判事例
今月号は、少し趣向を変えて、これまでの約30年間に及ぶ弁護士生活において私が担当した多数の離婚事件を基にして、「夫婦間の愛情と信頼の関係」について感じたことをつれづれなるままにお話ししてみようと思います。
憲法第24条は、「家族生活における個人の尊厳と両性の平等」という標題の下に、次のように規定しています。
第1項 「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」
第2項 「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」
憲法は、婚姻や家庭生活のあり方についての基本法として、婚姻や家庭生活のあるべき姿を示しています。すなわち、戦前の家制度や家長制度を中心とした婚姻関係や、家庭生活とは異なり、個人の尊厳と男女は本質的に平等であることを中心とした婚姻関係や、家庭生活を築くべきであるという理念を示しています。
次のような事例について、皆さまはどのように感じられることでしょうか。
「20代後半の男女が仕事の関係で知り合い、約1年の交際の後に入籍して晴れて夫婦になり、夫の実家(農家)で夫の両親と同居を始め、その半年後にはかわいい子ども(孫)も誕生しました。ところが、奥様と義理の両親との間で子ども(孫)の養育の方法や家事のやり方を巡って意見が食い違い、義理のご両親は、『嫁(奥様)の養育方針では孫に当家を継がせることはできない、嫁は当家の家風にはふさわしくない』などと広言するようになり、家庭生活もギクシャクするようになりました。夫は、妻よりも両親の言い分を聞くだけで、妻には我慢するように言うばかりです。そこで妻は、このような生活には耐えられない、ということで子どもを連れ実家へ帰り、別居生活となりました。そして、ついに結婚後2年に、性格の不一致を理由として離婚することになりました」
家の跡取りとしての子を産むのが嫁の勤め、嫁は家の働き手、などという昔ながらの家制度を中心とした結婚観に染まっている家庭では、息子さんの結婚についてもそのような結婚観で若夫婦を見るため、どうしても溝が生まれるのです。
このような家庭では、夫婦の合意で結婚はしたけれど、その夫婦の間には、個人の尊厳とか両性の本質的平等という価値観は生まれていないようです。
結婚生活において最も大切なことは、お互いに相手方を一人の人間として尊重して信頼し、その上で深い愛情が醸成されることではないでしょうか。これが夫婦の絆というものではないか、と考える今日この頃です。
934号 2018年12月23日
(45)規定の新設①
民法の改正があり、相続の分野では配偶者の居住権を保護する規定が新たに設けられました(2020年4月1日から施行)。具体的にはどのような規定でしょうか。
【事例】
A(80歳)と妻B(76歳)には、長女Cと二女Dの2人の子がおり、2人の子は嫁いでいる。BはA所有の建物にAと共に長年居住してきたが、最近Aが死亡した。Aは遺言をしていなかったことから、相続人であるB・C・Dで遺産分割協議をすることになったが、協議が整わない。
Bは、長年住み慣れた建物に今後も長く住みたいと思っているが、CやDは、Bが高齢でもあり持病もあるので一人で住むことには反対し、高齢者用住宅に入れたいと考えている。Bの希望を叶えることはできるであろうか?
Aの遺産は、Bと共に居住していた自宅(土地・建物の評価額2000万円)のほかに銀行預金が3000万円の合計5000万円があるが、負債はない。
【解説】
(1)現行の民法では、どうなるでしょうか。
上記の事例では、遺産分割協議が調わないので、家庭裁判所において遺産分割調停手続(調停が不成立の時は遺産分割の審判手続)で解決することになります。その場合、原則として、各自の法定相続分(配偶者のBは1/2、子C、Dは各自1/4)に応じて分割することになります。
その場合の分割の方法として、Bはその希望を取り入れて、居住していた土地・建物(2000万円)のほかに、銀行預金から500万円を相続し、子CとDは銀行預金の残り2500万円の1/2である1250万円を取得することが考えられます。
(2)現行の民法での配偶者の立場
これは一見すると、配偶者Bは建物と敷地の所有権を取得でき、そこに居住することができるからBの希望にも添うもののようにも考えられます。しかし、Bが銀行預金から相続できる預金額は、相続した土地・建物の評価額相当分(2000万円)が差し引かれるので、Bが銀行預金から相続できる財産はその分減額されることになります。つまり、Bは居住できる土地・建物は相続により取得できるが、今後の長い期間の生活費(例えば、水道光熱費や高齢者介護施設等に入所が必要になった場合の費用等)として必要になる現金・預金が少なくなり、場合によっては生活費に困ることも起こります。
(3)改正民法ー配偶者居住権の設定
そこで、このように、長年居住してきた土地・建物の所有権の帰属よりも、当該土地・建物に居住することができるようにして生存配偶者の生活の安定を図り、生存配偶者の居住権を保護するものとして、配偶者居住権という新たな権利が設けられました。
次回から、この新たに設けられた配偶者居住権についてお話ししていきたいと思います。
942号 2019年2月24日
(46)規定の新設②
前回は、今度の民法の改正手続で、配偶者居住権という新しい権利が設けられるということをお話しましたので、もう少し、この配偶者居住権についてお話しましょう。
配偶者の居住権を保護する居住権には、二つの種類があるといわれています。
ひとつは、「配偶者短期居住権」といわれるものです。これは、相続人間の遺産分割の終了時までの短期間、被相続人の生存配偶者(例えば、亡くなったご主人の奥さま)が無償で、その配偶者が居住している建物を使用することができるという居住権です。
もうひとつは、被相続人の生存配偶者が、相続を開始した当時に被相続人の所有していた建物に居住していた場合において、①遺産分割で配偶者居住権を取得することとされたとき、および、②遺贈により配偶者居住権が認められていたときは、その居住していた建物全部について、無償で使用収益することができるという権利です。これを配偶者居住権といい、配偶者に長期の居住権を保護するものです。
①の遺産分割で配偶者居住権を取得することとされたときというのは、審判手続で配偶者居住権を取得する場合です。遺産分割審判で相続人間でその旨の合意があると認められたとき、または、その合意がなくても、生存配偶者が配偶者居住権の取得を希望することを申し出た場合において、その配偶者の生活を維持するために特に配偶者居住権を認める必要があると認めるとき、ということです。
ところで、新民法903条4項は、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方が死亡した場合において生存配偶者に居住建物や敷地が遺贈または贈与されていたときは、その遺贈や贈与の価格は相続財産に含めない、すなわち、遺産分割の対象となる相続財産として扱わないといういわゆる持ち戻しの免除を定めていますが、配偶者居住権を贈与または遺贈していた場合も、その価格は相続財産には含めないという扱いがされます。この点でも配偶者には配慮されています。
配偶者居住権の存続期間は、遺産分割協議や遺言で特にその存続期間の定めがある場合や家庭裁判所の遺産分割審判で特別の定めがされた場合を除いて、生存配偶者の終身の間とされています。したがって、存続期間が満了したときや、配偶者居住権が認められた配偶者が死亡したときは、配偶者居住権は消滅します。
また、配偶者居住権は登記することもできますし、登記していると、当該建物の占有を妨害されている場合は妨害停止請求を、また第三者が居住建物を占有しているときは居住建物の返還請求をすることもできます。
なお、配偶者居住権は、配偶者自身の居住環境が継続できるようにして生存配偶者を特に保護しようとするものですから、これを譲渡することはできないことになっています。
951号 2019年4月28日
(47)遺留分制度①
前回に引き続き、民法改正に伴って見直される「遺留分制度」について、お話ししましょう。その前に、まず、現行民法では遺留分制度がどのような制度かを簡単に見ておきましょう。
遺留分制度は、兄弟姉妹以外の相続人、すなわち子、直系卑属及び配偶者に対し、相続財産の一定割合を留保することを認める(補償する)という制度です。被相続人は、本来、自分が所有する財産を自由に処分することができるのですが、被相続人と一定の身分関係にある相続人の扶養や相続財産の衡平(こうへい)な分配等を図るために、相続財産に対する一定の割合を補償するということです。その権利を有する相続人を遺留分権利者といいます。
遺留分の割合は、遺留分権利者全員に留保される相続財産に対する割合として、直系尊属のみが相続人である場合は被相続人の財産の3分の1、それ以外の場合は2分1となります。また、各遺留分権利者個人の遺留分は、前記の割合に対する各相続人の法定相続分の割合です。
例えば、相続人として被相続人の配偶者と子が3人いる場合は、配偶者と子が相続人ですから、相続人全員の遺留分は被相続人の財産の2分の1、配偶者個人の遺留分は、全遺留分2分の1に対する配偶者としての法定相続分2分の1ですから結局4分の1となります。また、3人の子の各個別の遺留分は、全遺留分2分の1に対して、子全員の法定相続分2分の1に対する各子の法定相続分3分の1の割合なので12分の1となります。
被相続人が生前に相続人の一人に対して贈与や遺贈をしていたことにより、ほかの相続人が自己の遺留分を侵害されたときは、遺留分減殺請求権という権利に基づいて、贈与や遺贈を受けた者に対して、遺留分減殺請求をすることができます。この請求は、通常、内容証明郵便によってしますが、遺留分減殺請求をすると、その対象とされた財産(例えば不動産)に対する遺留分権利者の(割合的)権利が回復され、共同相続人の共有になるとされています。これが現行の民法の建前です。
では、現行民法が改正されて、どのように変わるのでしょうか。また、そのように改正される理由は、どこにあるのでしょうか。相続の実務においてどのような変化が生じるのでしょうか。
次回から、これらについて解説していくことにしましょう。
958号 2019年6月23日
(48)遺留分制度②
前回に引き続き、民法改正に関わる遺留分制度の改正についてお話ししましょう。
現行の民法では、被相続人の遺言や生前贈与によって兄弟姉妹以外の相続人(直系尊属、配偶者、子)が遺留分を侵害されたときは、その相続人が遺言や贈与により財産を取得した者に対して遺留分減殺請求をすると、その効果として、その財産は直ちに遺産として復帰し、その結果、当該財産は相続人の共有財産となるというように理解されていました。
しかし、例えば、相続財産に工場等の事業用資産や会社の株式などがあった場合、遺留分減殺請求権が行使されると、複数の相続人のうち被相続人が残した会社事業を承継しない相続人との間でも共有関係が生じることになります。そうすると、残された会社事業が円滑に運営されないおそれが出てきます。また、被相続人が配偶者の老後を憂慮して配偶者へ自宅を生前贈与していたとします。そして相続人となる子がおり親元を離れて独立して生活している場合において、その相続人が遺留分減殺請求権を行使すると贈与を受けた自宅が共有関係となり、配偶者は安心して老後を送ることが出来なくなるおそれが生じます。
そこで、このようなことが起こらないようにするために、遺留分減殺請求権が行使されたからといって権利関係を元に戻す(共有関係になる)ような制度とはしないことにしました。すなわち、遺言や生前贈与等により相続人の遺留分を侵害するような事態になり、遺留分減殺請求権が行使された場合でも、遺言や生前贈与によって生じた権利関係はそのままとし、ただ、遺留分を侵害された相続人は、遺留分を侵害された額に相当する金銭の支払いを請求することができる、というように改正されることになりました(改正民法第1046条)。
そうすると、例えば前記の会社の事業承継と相続の関係でみると、事業を承継することになった長男が、遺言により事業用資産や株式を単独で取得しますが、ほかの相続人から遺留分減殺請求権(厳密には、遺留分侵害額請求権)を行使されたときは、その侵害額相当の金銭を支払えばよいことになるのです。また、自宅の贈与を受けた配偶者は、遺留分侵害請求権の行使を受けたときは、同じように、遺留分を侵害したという相続人からの遺留分侵害額請求に対し、その侵害額相当の金銭を支払うことで足り、自宅の共有関係は生じないことになります。
ただ、このように遺留分侵害額請求権を行使されたが、その侵害額相当の金銭を支払うことが直ちにできないこともあります。その場合は、遺留分侵害額請求を受けた受遺者又は受贈者の請求により、裁判所が相当の期限を許与することができることになっています。
962号 2019年8月18日
(49)自筆証書遺言
今回は、自筆証書遺言の方式緩和とその保管制度に関する民法改正のお話です。
現行の民法968条は、自筆証書遺言について①遺言者がその全文、日付及び氏名を自書してこれに押印し②自筆証書中の加除・訂正その他の変更は遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更場所に押印しなければ、その効力を生じないとしています。
このように厳格な要件を定めているのは、遺言者の最終の意思を確実にして、後日の紛争の発生をできるだけ防止しようとする趣旨とされています。しかし、厳格な要式の定めは、逆に言うと、自筆証書遺言の利用をためらうことにもなりますので、少し要件を緩和しようとこの度の改正になりました。
改正されたのは、遺言書と一体として財産目録を添付する場合は、その財産目録については、自書することまでは要求しない、すなわち自書以外の方法で財産目録を作成することもできるということになりました。これまでは、財産目録についても自書が要件でしたが、その要件が緩和されましたので、ワープロやパソコンによる作成もできますし、遺言者以外の者による代筆はもちろんのこと、不動産の登記事項証明書や預貯金通帳の写しを添付して遺産目録として使用することできることになりました。
ただし、財産目録が1枚を超えるときは各頁毎に遺言者の署名と押印を必要とし、特に自書によらない記載が両面に及ぶときはその両面に遺言者の署名と押印は必要です。また、財産目録の加除・訂正その他の変更をする場合は、遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更した場所に押印しなければ効力を生じません。この点は従前と同じです。
次に、自筆証書遺言の保管制度の新設です。公正証書遺言の場合は、公正証書遺言の原本が公証人役場で厳重に保管されますので、遺言書を紛失したり、偽造・変造されたりする心配はありません。しかし、自筆証書遺言の場合は、遺言者自身が自分で保管しなければなりませんが、どこに保管したかを忘れたり、関係者に偶然発見されて内容を見られたり偽造・変造される危険性もあります。
そこで、特別法(法務局における遺言書の保管等に間する法律)が制定され、自筆証書遺言の原本を公的機関が預かって保管する制度が新設されることになりました。これにより、自筆証書遺言は法務大臣の指定する法務局が「遺言書保管所」となります。因みに、現行民法での自筆証書遺言は、家庭裁判所による検認手続が必要ですが、保管手続に付された自筆証書遺言は、検認手続が不要とされています。
手続としては、法務局に対し、遺言書保管申請をして保管してもらうことになりますが、詳しい手続は法務局でお尋ね下さい。
衛藤二男法律事務所
TEL 282−8251 FAX 282−8261
受付時間 午前9時半〜午後5時半(月〜金)
967号 2019年10月20日
(50)最終回
「知って得する法律相談」は今回で50回目となり、最終回を迎えることになりました。長い間、お付き合い頂きましてありがとうございました。
さて、最終回の法律相談は、遺産分割における預貯金の取り扱いについてです。平成28年12月19日に最高裁判所大法廷の決定でこれまでとは異なる判断が示されましたので注意が必要です。
被相続人名義の預貯金を相続により相続人が取得する場合、遺産分割手続きを経る必要があるか、という問題については、これまで最高裁判所は、銀行等の金融機関に対する預貯金の返還請求債権は可分債権であるから、相続の開始により相続人間では当然に法定相続分の割合により分割されて各相続人に帰属するとされ、各共同相続人は、その相続分に応じて預貯金の返還請求債権を取得する、と判断していました。しかし、このたびの最高裁判所大法廷の決定は、「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当である」と判示して、これまでの判例を変更しました。
もちろん、これまでも、実際の遺産分割調停事件において、共同相続人間で預貯金を遺産分割の対象とする合意をすることは差し支えありませんでしたから、問題となるのは、そのような合意ができなかった場合に、各共同相続人が各自の法定相続分に応じて預貯金の返還請求債権を取得したとして単独で、その権利を行使することができるかということです。
では、これまでの最高裁判所の判断と、平成28年12月19日の判断では、具体的にはどのような違いがあるのでしょうか。事例で検討してみましょう。
「被相続人甲には、長男乙と次男丙がいる。甲は、生前に長男乙に対して1200万円の贈与をしており、これは乙の特別受益(民法903条)に該当する。甲死亡時の遺産としては1000万円の預金がある。
二男丙は、長男乙は生前に1200万円の生前贈与を受けており、これは特別受益に該当するから、民法903条により、乙には相続分はないので1000万円は丙が全額を相続するべきだという。他方、長男乙は、預金は法定相続分に応じて当然に分割されるから遺産分割の対象にはならず、乙の法定相続人2分の1に相当する500万円は乙が相続により取得したと主張している」
【解説】
この事例に先の最高裁判所の2つの考え方を当てはめると次のようになります。これまでの最高裁判所の考え方では、長男乙は、生前贈与分の1200万円プラス法定相続分の500万円の合計1700万円を取得しますが、二男丙は法定相続分の500万円しか取得できないことになります。これに対し、前記の新たな最高裁判所の考え方では、長男乙は生前贈与により1200万円を取得しておりこれが特別受益に該当し、法定相続分を超えているので、民法903条2項により、長男乙は、預金1000万円については相続分がありません。その結果、二男丙は預金1000万円を単独で相続することになります。
このように、共同相続人間では実際は大きな相違が生じると共に、金融機関に対して相続人が単独で自己の法定相続分に相当する預貯金返還請求債権を行使して預貯金の払い戻しを受けることができなくなります。その結果、共同相続人が被相続人の死亡後に被相続人の生前の債務を弁済しなければならない場合などは直ぐに対応できないこととなります。
そこで、今回の相続法の改正では、新たにその対応策となる規定(改正民法909条の2)が新設されましたので、詳しいことは改めてご相談下さい。
衛藤二男法律事務所
TEL:096−282−8251 FAX:096−282−8261
受付時間 9:30〜17:30(月〜金)